ホームページ制作には数十万円から数百万円の費用がかかることが一般的ですが、実は国や地方自治体が提供する補助金・助成金を活用することで、その負担を大幅に軽減できることをご存知でしょうか。特に2025年は、デジタル化推進の流れを受けて、ホームページ制作に活用できる補助金制度が充実しています。
しかし、補助金の種類は多岐にわたり、それぞれに異なる申請条件や手続きがあるため、「どの補助金を選べばよいのか」「自社は対象になるのか」「申請方法がわからない」といった悩みを抱える事業者の方も多いはずです。
そこで本記事では、2025年最新のホームページ制作に使える補助金・助成金について、個人事業主から中小企業まで幅広く活用できる制度を徹底解説します。各補助金の特徴、申請条件、具体的な申請手順、さらには申請時の注意点や成功のポイントまで、実践的な情報を網羅的にお伝えします。
記事執筆者:認定SEOコンサルタント 三田健司
ホームページ制作における補助金活用の基本知識
ホームページ制作に補助金を活用する前に、まず補助金制度の基本的な仕組みと、ホームページ制作がなぜ補助対象となるのかを理解することが重要です。
補助金・助成金・給付金の違いを理解する
補助金、助成金、給付金はいずれも返済不要の資金支援制度ですが、それぞれに明確な違いがあります。
補助金は、主に経済産業省や中小企業庁が管轄し、事業の発展や新規事業の立ち上げを支援する目的で提供されます。審査が厳格で採択率は低めですが、支給額が大きいのが特徴です。ホームページ制作では、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金などが該当します。
助成金は、主に厚生労働省が管轄し、雇用の安定や労働環境の改善を目的としています。要件を満たせば原則として支給されるため、補助金より受給しやすいですが、ホームページ制作に直接使える助成金は限定的です。
給付金は、特定の条件を満たす事業者への一時的な支援金で、コロナ禍での持続化給付金などが代表例です。現在、ホームページ制作に特化した給付金制度はありません。
なぜホームページ制作が補助対象になるのか
現代のビジネスにおいて、ホームページは単なる会社案内ではなく、重要な経営インフラとして位置づけられています。特に以下の観点から、国や自治体は積極的に支援を行っています。
デジタル化推進の観点:政府は「デジタル田園都市国家構想」を掲げ、地方を含む全国的なデジタル化を推進しています。ホームページは企業のデジタル化の第一歩として重要視されています。
生産性向上の観点:適切に構築されたホームページは、24時間365日働く営業マンとして機能し、問い合わせ対応の自動化、顧客データの収集・分析など、業務効率化に大きく貢献します。
販路拡大の観点:地域に限定されていた商圏を全国、さらには海外へと拡大できるホームページは、中小企業の成長戦略において不可欠なツールです。
補助金活用のメリットと注意すべきデメリット
補助金を活用することで得られるメリットは資金面だけではありません。
メリットとして、返済不要の資金により、キャッシュフローを圧迫せずに投資が可能になります。また、事業計画書の作成を通じて、自社の強みや課題が明確化されるという副次的効果もあります。補助金採択により、対外的な信用力が向上し、専門家のサポートを受けられる制度もあることから、経営改善のきっかけにもなります。
注意すべき点として、補助金は原則として後払いのため、一時的な資金立替が必要となります。申請書類の作成には相当な時間と労力がかかり、採択されない可能性があるため、確実な資金調達手段とは言えません。さらに、事業実施後も報告義務があり、不適切な使用は返還を求められることもあります。
2025年最新!ホームページ制作に使える主要補助金4選
2025年現在、ホームページ制作に活用できる代表的な補助金は4つあります。それぞれの特徴と最新情報を詳しく解説します。
IT導入補助金2025(通常枠)

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者のデジタル化を支援する最も代表的な補助金制度です。2025年度は制度内容が大幅に改訂され、より使いやすくなっています。
補助対象者 中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)で、以下の要件を満たす事業者が対象です。
| 業種分類 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
補助内容と補助率は、補助額が最大450万円、補助率が1/2以内となっています。対象となるITツールは事前に登録されたものに限られますが、ホームページ制作も含まれています。
2025年度の主な変更点として、クラウド利用料の補助期間が最大2年間に延長されました。また、インボイス対応機能を含むツールは補助率が2/3に優遇され、セキュリティ対策推進枠が新設されて、サイバーセキュリティ対策を含むホームページ制作も対象となりました。
申請スケジュール(2025年度)
- 第1次締切:2025年3月31日
- 第2次締切:2025年5月31日
- 第3次締切:2025年7月31日
- 第4次締切:2025年9月30日
IT導入補助金2025公式サイトで最新情報を確認できます。
小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、従業員数が少ない事業者に特化した補助金で、ホームページ制作費用も広報費として補助対象になります。
補助対象者 小規模事業者(個人事業主を含む)で、以下の従業員数以下の事業者が対象です。
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
補助内容と補助率は枠によって異なります。通常枠では補助上限50万円(補助率2/3)、賃金引上げ枠では補助上限200万円(補助率2/3、赤字事業者は3/4)、卒業枠・後継者支援枠・創業枠はいずれも補助上限200万円(補助率2/3)となっています。
ホームページ制作における注意点として、ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4が上限となります。単なるホームページ制作だけでなく、販路開拓の具体的な計画が必要で、ウェブ広告費なども組み合わせて申請することが推奨されています。
申請に必要な書類
- 経営計画書(様式2)
- 補助事業計画書(様式3)
- 事業支援計画書(商工会・商工会議所が発行)
- 補助金交付申請書(様式5)
- 宣誓・同意書(様式6)
事業再構築補助金

事業再構築補助金は、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開や業態転換などの事業再構築を支援する補助金です。
補助対象となる事業再構築の類型には、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン強靭化、リスキリング・労働移動支援があります。
補助金額・補助率
| 申請枠 | 従業員数 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 成長枠 | 20人以下 | 2,000万円 | 1/2(大規模な賃上げを行う場合2/3) |
| 21〜50人 | 4,000万円 | 1/2(大規模な賃上げを行う場合2/3) | |
| 51〜100人 | 5,000万円 | 1/2(大規模な賃上げを行う場合2/3) | |
| 101人以上 | 7,000万円 | 1/2(大規模な賃上げを行う場合2/3) |
ホームページ制作が対象となるケースとしては、オンラインサービス展開のためのECサイト構築、新事業のPRサイト制作、顧客データベースと連携した会員制サイトの構築、多言語対応サイトによる海外展開などがあります。
認定支援機関の関与が必須となっており、事業再構築補助金の申請には、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援が必要です。税理士、中小企業診断士、金融機関などが該当します。
詳細は、事業再構築補助金のサイトへ
ものづくり補助金
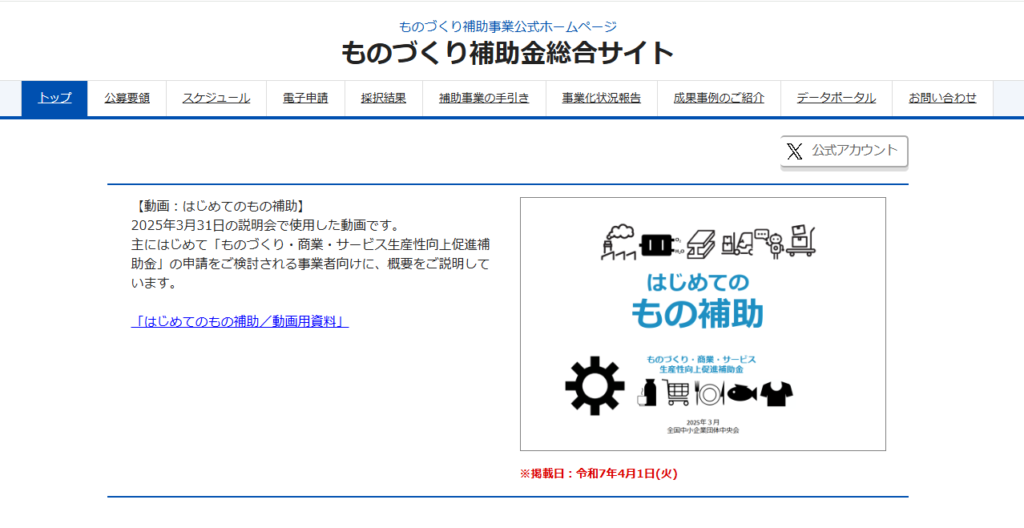
ものづくり補助金は、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を支援する補助金で、IT投資も対象に含まれます。
補助対象者は中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)で、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有すること、資本金又は従業員数が規定の範囲内であること、3〜5年の事業計画を策定し、従業員に表明していることが要件となります。
補助金額・補助率(通常枠)は、補助上限が750万円〜1,250万円、補助率が1/2(小規模事業者・再生事業者は2/3)です。
デジタル枠の活用により、DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービスの開発には「デジタル枠」が適用され、補助上限が最大1,500万円まで引き上げられます。
ホームページ制作における採択のポイントは、単なるホームページ制作ではなく、革新的なサービス提供の仕組みが必要です。AIやIoTなどの先端技術を活用した付加価値の高いサイト構築や、業界の常識を覆すような新しいビジネスモデルの提示が求められます。
詳細は、ものづくり補助金総合サイトへ
地方自治体の補助金・助成金活用ガイド
国の補助金以外にも、各地方自治体が独自に実施している補助金制度があります。地域密着型の支援が多く、比較的採択率が高いのが特徴です。
東京都の主な補助金制度
販路拡大助成事業は、都内中小企業を対象に、補助率2/3以内、限度額150万円で支援します。展示会出展費用やホームページ制作費用が対象となります。
創業助成事業は、都内での創業を具体的に計画している個人又は創業から5年未満の中小企業者等を対象に、補助率2/3以内、限度額300万円で支援します。広告費の一部としてホームページ制作費用も対象となります。
大阪府の主な補助金制度
大阪産業局 販路開拓支援補助金は、大阪府内の中小企業を対象に、補助率1/2、限度額50万円で支援します。BtoB、BtoC問わずホームページ制作が対象となります。
地方自治体補助金の探し方
地方自治体の補助金情報は以下の方法で効率的に探すことができます。
- J-Net21(中小企業ビジネス支援サイト)の補助金・助成金検索
- 各都道府県・市区町村の公式ホームページ
- 地域の商工会議所・商工会への問い合わせ
- 中小企業支援センターでの相談
自治体補助金申請の注意点
自治体補助金は予算枠が小さく、早期に締め切られることが多いため注意が必要です。地域内の事業者限定など、対象要件が細かく設定されており、申請期間が短期間の場合が多いため、情報収集が重要となります。また、国の補助金との併用ができない場合があることも留意すべきポイントです。
補助金申請から受給までの詳細プロセス
補助金の申請から受給までは、一般的に以下の流れで進みます。各ステップでの注意点を詳しく解説します。
ステップ1:事前準備と情報収集
補助金申請の成功は、事前準備の質で大きく左右されます。
必要な準備事項として、まず自社の現状分析が重要です。経営課題の明確化、ホームページ制作の目的と期待効果の整理、必要な機能や予算規模の検討を行います。次に、補助金制度の比較検討を行い、各補助金の特徴と自社への適合性評価、申請要件の確認(特に除外要件に注意)、スケジュールと自社の事業計画との整合性確認を実施します。
ステップ2:事業計画書の作成
事業計画書は補助金採択の最重要書類です。審査員を納得させる計画書作成のポイントを解説します。
事業計画書に含めるべき要素
現状分析と課題設定では、SWOT分析による自社の強み・弱みの明確化、市場環境と競合状況の分析、解決すべき経営課題の具体的な提示を行います。
ホームページ制作の必要性では、現状の問題点(アクセス数、問い合わせ数、売上への貢献度など)、競合他社との比較、顧客ニーズとの乖離を明確に示します。
実施内容の詳細には、制作するホームページの具体的な機能、導入するシステムやツール、制作スケジュール、費用内訳(見積書を添付)を記載します。
期待効果と数値目標では、売上増加見込み(具体的な数値で)、業務効率化による工数削減効果、新規顧客獲得見込み数、ROI(投資収益率)の試算を示します。
実現可能性の証明として、実施体制(社内体制と外部委託先)、類似プロジェクトの実績、リスク対策を明記します。
ステップ3:申請手続きの実施
オンライン申請が主流となっている現在、以下の点に注意が必要です。
GビズIDの取得は多くの補助金で必要となるGビズIDプライムアカウントの取得に2〜3週間かかるため、早めの準備が重要です。
電子申請システムの操作では、入力内容の一時保存機能を活用し、アップロードファイルのサイズ制限に注意します。申請締切時間直前はアクセス集中により繋がりにくくなるため、余裕を持った申請が必要です。
申請時のチェックポイント
- 必須項目の入力漏れがないか
- 添付書類に不足がないか
- 申請内容と添付書類の整合性
- 誤字脱字がないか(特に金額部分)
ステップ4:審査対応
書類審査を通過すると、面接審査やヒアリングが実施される場合があります。
面接審査の準備では、事業計画の要点を5分程度で説明できるよう準備し、想定質問への回答準備、補足資料の準備(デモ画面、競合分析資料など)を行います。
よくある質問例として、なぜ今ホームページ制作が必要なのか、他の手段では解決できないのか、投資効果をどのように測定するか、失敗した場合のリスク対策は、といった質問が想定されます。
ステップ5:採択後の手続き
採択通知を受けた後も、気を抜けない重要な手続きが続きます。
交付申請の実施では、採択=補助金確定ではないことを理解し、改めて交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
事業の実施における注意点として、以下の点に留意が必要です。詳細な対策については「申請時の落とし穴と対策」セクションで解説しています。
- 交付決定前の発注・契約は補助対象外
- 相見積もりの取得が必要(原則3社以上)
- 仕様変更が生じた場合は事前に変更申請が必要
- 支払いは銀行振込が原則(現金払いは要注意)
ステップ6:実績報告と補助金受給
事業完了後、定められた期限内に実績報告を行います。
実績報告に必要な書類は、実績報告書、経費明細書、証拠書類(請求書、領収書、銀行振込明細等)、成果物(制作したホームページの画面キャプチャ等)、その他指定された書類です。
補助金の受給は、実績報告の審査完了後に行われ、通常、実績報告から1〜2ヶ月程度かかります。
補助金申請の成功率を高める実践的テクニック
補助金の採択率を高めるための具体的なテクニックを、実際の成功事例を交えて解説します。
差別化ポイントの明確化
審査員は多数の申請書を短時間で審査します。その中で目に留まる申請書にするためのポイントを紹介します。
独自性のアピール方法
地域性を活かした提案では、地域の特産品のEC展開、観光資源を活用したインバウンド対応、地域課題解決型のビジネスモデルなどが効果的です。
業界の常識を覆す提案では、従来オフラインのみだった業界のDX化、BtoBビジネスのBtoC展開、サブスクリプションモデルの導入などが注目されます。
社会課題への対応では、SDGsへの貢献、高齢者・障害者への配慮(アクセシビリティ)、地方創生への寄与などをアピールすることが有効です。
数値目標の設定方法
曖昧な目標設定は不採択の大きな要因です。説得力のある数値目標の立て方を解説します。
SMART原則に基づく目標設定では、Specific(具体的)として「売上向上」ではなく「ECサイト経由の売上」、Measurable(測定可能)として「多くの顧客」ではなく「月間1,000人の新規顧客」、Achievable(達成可能)として過度に楽観的でない現実的な数値、Relevant(関連性)として経営課題と直結した指標、Time-bound(期限)として「3年後」ではなく「2026年3月末」という具体的な設定を行います。
具体的な数値目標の例
- ホームページ経由の問い合わせ数:現状月10件→目標月50件(1年後)
- ECサイトの売上:現状0円→目標月商300万円(2年後)
- 検索順位:主要キーワードで現状圏外→目標10位以内(6ヶ月後)
- ページ滞在時間:現状1分30秒→目標3分以上(3ヶ月後)
専門家活用のメリットと注意点
補助金申請において、専門家の活用は成功率を大きく左右します。
専門家活用の利点として、採択率の向上(プロは採択ポイントを熟知)、申請書作成の時間短縮、事業計画のブラッシュアップ、申請後のフォローアップがあります。
専門家選びの注意点では、成功報酬型と着手金型の違いを理解し、過去の実績(採択率、対応業種)を確認し、サポート範囲を明確にし(申請のみか実績報告までか)、費用対効果を慎重に検討する(補助金額に対する報酬の妥当性)ことが重要です。
良い専門家の見分け方は、具体的な改善提案をしてくれる、デメリットやリスクも説明する、過度な期待を持たせない、アフターフォローが充実している、といった点で判断できます。

申請時の落とし穴と対策(失敗事例から学ぶ)
実際の不採択事例から、陥りやすい落とし穴とその対策を解説します。
よくある不採択理由と対策
- 事業計画の具体性不足
失敗例:「ホームページを作って売上を伸ばしたい」という漠然とした計画
対策:ターゲット顧客の明確化(年齢、性別、居住地、興味関心等)、具体的な集客施策(SEO対策、リスティング広告、SNS活用等)、成果測定方法の明示(Google Analytics導入、コンバージョン測定等)を行います。
- 費用対効果の説明不足
失敗例:「300万円かけてホームページを作れば売上が上がるはず」
対策:投資回収期間の明示(例:18ヶ月で投資回収)、段階的な効果測定(3ヶ月後、6ヶ月後、1年後の目標設定)、類似事例やベンチマークの提示を行います。
- 自社の強みを活かせていない
失敗例:競合他社と同じような一般的なホームページ制作計画
対策:自社独自の技術やノウハウの活用、既存顧客の声を反映した機能設計、業界特有の課題への対応を盛り込みます。
書類不備による不採択を防ぐチェックリスト
書類不備は最も避けるべき不採択理由です。以下のチェックリストで確認しましょう。
必須書類チェックリスト
- [ ] 申請書(指定様式を使用しているか)
- [ ] 事業計画書(必要項目がすべて記載されているか)
- [ ] 決算書類(直近2期分、税務署の受付印があるか)
- [ ] 見積書(有効期限内か、詳細な内訳があるか)
- [ ] 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に取得したものか)
- [ ] 納税証明書(未納がないことの証明)
- [ ] その他補助金ごとの必要書類
内容確認チェックリスト
- [ ] 誤字脱字がないか(特に金額、日付)
- [ ] 計算ミスがないか(合計金額、補助金額等)
- [ ] 書類間で矛盾がないか(申請書と見積書の金額等)
- [ ] 専門用語に説明があるか
- [ ] 図表が見やすいか(文字サイズ、配色等)
採択後の失敗を防ぐポイント
採択されても、その後の手続きでつまずくケースも少なくありません。
よくある採択後の失敗
交付申請の遅延・失念は、採択通知に安心して交付申請を忘れるケースです。対策として、採択通知受領後、即座にスケジュール確認を行います。
計画変更への対応ミスは、無断で仕様変更や金額変更を行うケースです。対策として、些細な変更でも事前に事務局へ相談します。
証拠書類の不備は、領収書や納品書を紛失するケースです。対策として、すべての書類をデジタル保存し、原本も整理保管します。
実績報告の遅延は、期限ギリギリで準備を始めて間に合わないケースです。対策として、事業完了前から報告書作成を開始します。
補助金を最大限活用するためのホームページ制作戦略
単に補助金を受給するだけでなく、真にビジネスに貢献するホームページを制作するための戦略を解説します。
補助金を活用した費用対効果の高い制作方法
段階的な機能実装アプローチ
補助金には上限額があるため、優先順位を付けた機能実装が重要です。
第1段階(必須機能)では、レスポンシブデザイン(スマートフォン対応)、SSL対応(セキュリティ確保)、基本的なSEO対策、お問い合わせフォーム、Google Analytics導入を実装します。
第2段階(売上直結機能)では、ECカート機能、会員登録・マイページ機能、予約システム、顧客管理システム(CRM)連携を追加します。
第3段階(付加価値機能)では、AIチャットボット、多言語対応、AR/VR機能、ビッグデータ分析機能などの先進的な機能を導入します。
コストを抑えつつ品質を確保する方法
CMSの活用により、WordPress、Movable Typeなどの活用で開発コスト削減し、更新作業の内製化により運用コスト削減を図ります。
クラウドサービスの組み合わせでは、AWS、Google Cloud等のインフラ活用と、SaaS型のマーケティングツール連携により、効率的なシステム構築を実現します。
アジャイル開発の採用により、小規模リリースの繰り返しでリスク低減し、ユーザーフィードバックを随時反映することで、より良いホームページを構築します。
制作会社選定のポイント
補助金を活用する場合、制作会社選びには通常以上の注意が必要です。
必須確認事項
補助金対応の経験では、過去の補助金案件実績、必要書類作成への協力体制、相見積もりへの対応可否を確認します。
技術力と実績では、ポートフォリオの確認、同業他社の制作実績、技術者のスキルレベルを評価します。
サポート体制では、納品後の保守運用体制、トラブル時の対応速度、教育研修の実施可否を確認します。
見積もり比較時の注意点として、補助金申請では原則3社以上の相見積もりが必要ですが、単純な価格比較は危険です。機能要件の充足度、使用する技術やツール、納期と開発スケジュール、保守運用費用(ランニングコスト)、追加開発時の費用体系を総合的に比較検討する必要があります。
補助金活用後の運用・改善戦略
ホームページは制作して終わりではありません。継続的な改善が成功の鍵です。
PDCAサイクルの実践
Plan(計画)では、KPI設定(PV数、CVR、直帰率等)、改善施策の立案、予算とスケジュール策定を行います。
Do(実行)では、コンテンツの定期更新、A/Bテストの実施、広告運用の最適化を実施します。
Check(評価)では、アクセス解析、ヒートマップ分析、ユーザーアンケートを通じて効果を測定します。
Action(改善)では、問題点の特定と対策、成功事例の横展開、次期計画への反映を行います。
継続的な補助金活用
一度の補助金でホームページを制作した後も、IT導入補助金(機能追加やツール導入)、小規模事業者持続化補助金(広告宣伝費として)、各種自治体補助金(リニューアルや多言語化等)などを活用して継続的な改善が可能です。
2025年度の補助金動向と今後の展望
補助金制度は社会情勢や政策方針により変化します。2025年度の最新動向と今後の展望を解説します。
2025年度の主な制度変更点
デジタル化推進の加速では、DX関連の補助率優遇措置の拡大、AI・IoT活用への重点支援、サイバーセキュリティ対策の義務化傾向が見られます。
グリーン化との連携では、環境配慮型ビジネスへの優遇、ペーパーレス化推進との連携、カーボンニュートラルへの貢献度評価が重視されています。
地方創生との連動では、地方移転や地方展開への支援強化、地域資源活用型ビジネスの優遇、関係人口創出への貢献評価が行われています。
今後予想される補助金トレンド
成果連動型補助金の増加により、従来の設備投資型から、実際の成果(売上増加、雇用創出等)に応じた補助金へのシフトが予想されます。
業種別特化型支援の充実により、画一的な支援から、業種特性に応じたきめ細かな支援への移行が進むでしょう。
継続的な支援体制の構築により、単発の補助金から、事業の成長段階に応じた継続的な支援への転換が期待されます。
補助金に頼らない経営体質の構築
補助金はあくまでも事業成長の「きっかけ」です。重要なのは、補助金を活用して構築した仕組みを、いかに自走させるかです。
自立的な成長への道筋は、補助金で構築した基盤の最大活用、収益モデルの確立と改善、再投資による継続的な強化、新たな収益源の開拓という流れで進めることが重要です。
まとめ:補助金を活用したホームページ制作成功への道
ホームページ制作における補助金活用は、資金面のメリットだけでなく、事業計画の見直しや経営改善の機会にもなります。2025年は特に、デジタル化推進の流れから、ホームページ制作への支援が充実しています。
成功のための重要ポイント
- 自社に最適な補助金の選定
- 説得力のある事業計画書の作成
- 確実な申請手続きの実施
- 制作会社との適切な連携
- 補助金活用後の継続的な改善
補助金申請は確かに手間がかかりますが、その過程で得られる経営改善の視点や、実際に受給できる資金は、企業成長の大きな推進力となります。本記事で解説した内容を参考に、ぜひ補助金を活用した戦略的なホームページ制作に挑戦してください。
最後に、補助金制度は頻繁に更新されるため、必ず各補助金の公式サイトで最新情報を確認することをお勧めします。また、不明な点は各補助金の事務局や、地域の支援機関に相談することで、より確実な申請が可能となります。
デジタル時代において、ホームページは企業の顔であり、最も重要な営業ツールの一つです。補助金を賢く活用し、競争力のあるホームページを構築することで、ビジネスの新たな可能性を切り開いていきましょう。

記事執筆・株式会社アクセス・リンク 代表取締役
Webサイト制作歴10年以上の経験を元にSEOコンサルティングを行い、延べ1,000件以上のサポート実績を誇ります。個人事業主や中小企業向けのホームページ制作やSEOコンサルティングを得意としています。
(社)全日本SEO協会 認定SEOコンサルタント


コメント