ホームページは企業やサービスの顔となるWebサイトです。しかし、せっかく時間とコストをかけて作成したホームページが、思うような成果を上げられないケースが少なくありません。その原因は、ホームページ制作や運用において「やってはいけないこと」を知らずに行ってしまっているからかもしれません。
多くの企業がホームページを持つ現代では、ユーザーの目は肥えており、少しでも不便さや違和感を感じれば、すぐに別のサイトへ移動してしまいます。そのため、ホームページ制作・運用において避けるべきポイントを知ることは非常に重要です。
そこで本記事では、ホームページ制作のプロフェッショナルが、ホームページでやってはいけない32個のポイントを解説します。企画・設計段階、制作会社選びから、SEO対策、運用・保守に至るまで、各段階で陥りがちな失敗とその解決策を詳しく解説します。これからホームページを作る方はもちろん、すでに運用している方も、自社サイトのチェックリストとしてぜひ活用してください。
記事執筆者:認定SEOコンサルタント 三田健司
ホームページの企画・設計でやってはいけないこと
ホームページ制作の最初のステップである企画・設計段階でのミスは、後の工程にも大きく影響します。効果的なホームページ制作の土台を築くため、以下の失敗を避けましょう。
1. 目的を明確にせずに制作を始める
ホームページを作る目的が明確でないまま制作を始めることは、大きな失敗の元です。「とりあえずホームページが必要だから」という理由だけでは、効果的なサイトは作れません。新規顧客の獲得、ブランドイメージの向上、商品・サービスの販売促進、採用活動の強化、会社情報の発信など、様々な目的が考えられますが、これらを整理せずに進めると、デザインやコンテンツの方向性が定まらず、結果として「何のためのホームページなのか」が分からないサイトになってしまいます。
【解決策】 ホームページ制作の前に、このホームページで達成したいことは何か、どのような行動をユーザーに取ってほしいか、成功の指標は何かといった点について十分に検討することが重要です。これらの目的を文書化し、関係者全員で共有することで、ブレのない制作が可能になります。複数の目的がある場合は、優先順位をつけることも忘れないようにしましょう。
2. ターゲットを設定しない
「誰に向けたホームページなのか」を考えずに制作すると、結果として「誰にも響かない」ページになってしまいます。ターゲットによって、使うべき言葉遣い、デザイン、コンテンツの内容は大きく変わるものです。例えば、10代の若者向けと60代以上のシニア層向けでは、好まれるデザインや理解しやすい言葉遣いが大きく異なります。ターゲットを明確にしないまま制作すると、どの層にも刺さらないサイトになる可能性が高いです。
【解決策】 ターゲットとなるユーザー像(ペルソナ)を具体的に設定することが重要です。ペルソナ設定では、年齢・性別・職業・家族構成といった基本情報だけでなく、趣味・関心事、抱えている課題や悩み、インターネットの利用習慣、情報収集の方法なども考慮します。このようなペルソナを設定することで、「このユーザーに向けて話しかける」イメージで内容を考えられるようになり、より効果的なコミュニケーションが可能になります。複数のターゲット層がある場合は、優先度の高いターゲットから順に対応を検討するとよいでしょう。
3. 数値目標を設定しない
「なんとなくアクセスが増えればいい」という曖昧な目標では、ホームページの効果を測定できません。具体的な数値目標がないと、改善すべきポイントも見えてきません。成果を明確に把握するためには、測定可能な指標を設定することが不可欠です。
【解決策】 以下のような具体的な数値目標を設定することをおすすめします:
| 目標の種類 | 例 | 測定方法 |
|---|---|---|
| アクセス数 | 月間PV 10,000件 | Googleアナリティクス |
| コンバージョン | お問い合わせ数 月50件 | お問い合わせフォーム集計 |
| 滞在時間 | 平均滞在時間 3分以上 | Googleアナリティクス |
| 離脱率 | トップページの離脱率 40%以下 | Googleアナリティクス |
このように目標を設定することで、達成状況を定期的に確認し、必要に応じて改善策を講じることができます。数値目標は、サイトの規模や業界特性に合わせて現実的なものを設定し、定期的に見直すことも大切です。
4. 競合分析を行わない
自社のホームページだけを見て制作を進めると、業界標準から外れたり、ユーザーの期待に応えられなかったりする可能性があります。競合サイトの分析は、業界のトレンドや標準を知るために欠かせません。
【解決策】 最低でも3〜5社の競合サイトを分析することをおすすめします。分析の際は、サイト構成、提供されている情報の種類、デザインの特徴、CTA(Call To Action)の設置方法、強みの表現方法などに注目するとよいでしょう。
競合分析で確認すべき主なポイントを表にまとめました:
| 分析項目 | 確認ポイント | 活用方法 |
|---|---|---|
| サイト構成 | メニュー構成、ページ階層 | ユーザーが期待する情報構造を理解する |
| コンテンツ | 提供情報の種類、詳細の度合い | 業界で標準とされる情報を把握する |
| デザイン | 色使い、レイアウト、画像使用 | 業界のデザイントレンドを参考にする |
| CTA(行動喚起) | ボタンの配置、表現方法 | 効果的な誘導方法を学ぶ |
| 差別化ポイント | 強みの表現方法 | 自社の独自性を強調する方法を検討する |
ただし、競合分析は「真似をする」ためではなく、「業界標準を知り、そこから差別化するため」のものであることを忘れないようにしましょう。
制作会社選びでやってはいけないこと
ホームページ制作を外注する場合、制作会社選びは成功の鍵を握ります。適切なパートナーを見つけるため、以下のような失敗を避けましょう。
5. 見積もりを1社だけで決める
複数の制作会社から見積もりを取らずに決めてしまうと、適正価格や提供されるサービスの違いが分からず、後悔する可能性があります。市場相場を知るためにも、比較検討は欠かせないプロセスです。
【解決策】 最低でも3社以上から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。見積もりを比較する際は、単純な価格だけでなく、総額と内訳、提案内容の質、コミュニケーションの取りやすさ、実績やポートフォリオ、アフターサポートの内容など、総合的に判断することが重要です。
各社の強みや特徴を把握し、自社のニーズに最も合った制作会社を選ぶようにしましょう。また、見積もり依頼時には同じ条件で依頼することで、公平な比較が可能になります。
6. 価格の安さだけで選ぶ
「とにかく安いところで」と価格のみで選定すると、品質や機能面で妥協せざるを得なくなり、結果的に使いづらいサイトになることがあります。安価なホームページ制作サービスでは、テンプレートの使い回しや、低品質な素材の使用、アフターサポートの不足といった問題が生じる可能性があります。
【解決策】 ホームページ制作会社を選ぶ際は、価格と価値のバランスを考慮することが重要です。価格だけでなく、品質(過去の制作実績)、スピード(納期の適切さ)、サポート(アフターフォローの内容)などを総合的に評価しましょう。
特に、公開後のサポート体制は重要です。トラブル発生時や更新が必要になったときに、適切なサポートが受けられるかを事前に確認しておくことで、長期的な運用がスムーズになります。
結果的に、安すぎる制作会社を選ぶことで生じる問題を修正するコストの方が、当初から適正な価格で質の高いサービスを選ぶよりも高くつくことがあります。
7. 契約内容をしっかり確認しない
細かい契約内容を確認せずに契約すると、後から「そこまでは含まれていない」と追加料金を請求されるケースがあります。曖昧な契約内容は、制作途中のトラブルや予想外の出費の原因となります。
【解決策】 契約前には、納品物の詳細(制作されるページ数や機能)、修正回数の制限、著作権の帰属、保守・運用サポートの範囲と期間、追加料金が発生する条件などを必ず確認しましょう。
特に重要なのは「含まれないもの」を明確にすることです。例えば、「写真撮影は含まれない」「SEO対策は基本的な項目のみ」といった制限事項を事前に把握しておくことで、後からのトラブルを防げます。
契約書の内容で不明点があれば、必ず契約前に質問して解消しておきましょう。また、口頭での約束は後々のトラブルの元になりやすいため、重要な事項は必ず書面で残すようにしてください。明確な契約内容を持つことは、発注者側にとっても制作会社側にとっても、スムーズなプロジェクト進行の鍵となります。
8. 自社で更新できない仕組みを選ぶ
制作会社に依頼する際、更新のたびに制作会社に依頼しなければならないシステムを選ぶと、スピーディーな情報更新ができなくなります。これは特に、ニュースや商品情報など、頻繁に更新が必要なコンテンツがある場合に大きな問題となります。更新の都度、制作会社への依頼と費用が発生するため、コスト面でも運用面でも非効率です。
【解決策】 可能な限り、自社で更新可能なCMS(Content Management System)を導入しましょう。WordPressなどの一般的なCMSであれば、社内でも比較的簡単に更新作業が行えます。システム選定時には、実際に管理画面を操作してみて、使いやすさを確認することも重要です。
また、納品時には更新マニュアル、管理画面へのアクセス情報(ID・パスワード)、簡単な操作レクチャーなどを必ず受け取りましょう。さらに、社内で更新作業を担当する人材を決め、基本的な操作方法のトレーニングを受けておくことで、スムーズな運用が可能になります。CMSの選択は、将来的な拡張性も考慮し、業界標準のものを選ぶことをおすすめします。
サイト構築でやってはいけないこと
サイトの基盤となる部分での失敗は、後から修正するのが非常に困難です。強固な基盤を構築するため、以下のような失敗を避けましょう。
9. 無料サーバーや低品質サーバーを使用する
無料または非常に安価なレンタルサーバーは、安定性や速度、セキュリティ面で問題がある場合が多く、ビジネス用途には適していません。
無料・低品質サーバーを使用すると、突然のサービス終了リスク、広告の強制表示、アクセス集中時の表示速度低下、セキュリティ対策の不十分さ、データバックアップの不備などの問題が生じる可能性があります。これらの問題は、ユーザーの信頼を損ない、ビジネスチャンスの損失につながることもあります。
【解決策】 ビジネス用途であれば、信頼性の高い有料サーバーを選びましょう。月額1,000円〜3,000円程度の料金で、安定したサービスを利用できます。サーバー選定時には、以下の表のようなポイントを確認するとよいでしょう。
| 確認ポイント | 推奨される基準 | 理由 |
|---|---|---|
| 稼働率(アップタイム) | 99.9%以上 | サイトの安定稼働を保証 |
| サポート体制 | 24時間対応 | 緊急時にも対応可能 |
| バックアップ | 自動バックアップ機能 | データ消失リスクの軽減 |
| セキュリティ | WAF、マルウェア対策など | 不正アクセスからの保護 |
| ハードウェア | 高速なSSD搭載 | 表示速度の向上 |
特に、アクセス数が多いサイトや、EC(電子商取引)機能を持つサイトでは、サーバーの品質が直接ビジネスに影響するため、十分な検討が必要です。
10. ドメインを適当に選ぶ
会社名やサービス名と無関係なドメイン、覚えにくいドメイン、紛らわしいドメインを選ぶと、ユーザーがアクセスしにくくなります。ドメイン名は企業やブランドのオンライン上のアイデンティティであり、一度決めると変更が難しいため、慎重に選ぶ必要があります。
【解決策】 適切なドメインを選ぶ際は、会社名やサービス名を含み、短く覚えやすく、発音しやすいものを選びましょう。また、ハイフンやアンダーバーは極力使わず、将来的な展開も視野に入れることが重要です。国際展開の可能性がある場合は、.comなどの国際的なトップレベルドメインを選ぶとよいでしょう。
ドメイン選びで避けるべき主な問題点としては、他社の商標やブランド名に似たドメインの取得があります。これは法的トラブルを引き起こす可能性があるため注意が必要です。また、過去に使用されていたドメインを取得する場合は、そのドメインの履歴(スパムサイトだったなど)を確認することも重要です。良質なドメインは企業の信頼性を高め、覚えやすさによってリピーターの獲得にも貢献します。
11. SSL対応していない
SSLは、サイトとユーザー間の通信を暗号化する技術です。現在のWebブラウザでは、SSL未対応サイトに「保護されていない通信」という警告を表示するため、ユーザーに不安を与える可能性があります。この警告表示は、ユーザーの信頼を損ない、離脱率の上昇につながることがあります。
【解決策】 必ずSSL対応(https://で始まるURL)にしましょう。多くのレンタルサーバーでは、無料でSSL証明書を発行できるサービスを提供しています。SSL対応のサイトは、ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示され、ユーザーに安心感を与えます。
SSL対応は特に、個人情報(名前、メールアドレス、住所など)、クレジットカード情報、ログイン情報(ID・パスワード)などを扱うサイトでは必須となります。また、GoogleはSSL対応サイトを検索順位で優遇する傾向があるため、SEO対策の観点からも重要です。既存サイトをSSL対応に切り替える場合は、リダイレクト設定を適切に行い、内部リンクや外部リンクの移行にも注意が必要です。
12. モバイル対応(レスポンシブデザイン)しない
現在、インターネットアクセスの約70%以上はスマートフォンだといわれています。モバイル対応していないサイトは、多くのユーザーに使いづらい体験を提供することになり、離脱率の上昇やビジネスチャンスの損失につながります。
【解決策】 レスポンシブデザイン(画面サイズに応じて自動的にレイアウトが調整されるデザイン)を採用しましょう。現代のCMSやテンプレートの多くは、標準でレスポンシブデザインに対応しています。モバイル対応の重要性は年々高まっており、Googleもモバイルフレンドリーなサイトを検索順位で優遇しています。
なお、完成したサイトは必ず複数のデバイス(スマートフォン、タブレット、PC)で表示確認を行い、すべての環境で適切に表示・機能するかをチェックすることが重要です。
特に注意すべき点としては、タップできる要素(ボタンやリンク)のサイズ、フォントの読みやすさ、画像の表示方法などがあります。モバイルユーザーの快適な閲覧体験を確保することは、現代のウェブデザインにおいて最も基本的な要件の一つです。
13. ページ表示速度を考慮しない
ページの表示が遅いと、ユーザーはイライラし、離脱する確率が高まります。Googleの調査によれば、3秒以上の表示時間がかかるとユーザーの約40%が離脱するというデータもあります。表示速度はユーザー体験だけでなく、検索エンジンでの評価にも影響する重要な要素です。
【解決策】 ページ表示速度を改善するためには、画像の最適化(適切なサイズと圧縮)、不要なプラグインの削除、キャッシュの活用、JavaScript・CSSの最小化、高速なホスティングサービスの利用などの対策が効果的です。
特に画像の最適化は比較的簡単に実施でき、大きな効果が期待できます。画像ファイルのサイズを適切に圧縮し、表示サイズに合わせてリサイズすることで、読み込み時間を大幅に短縮できます。また、最近のウェブ技術では、遅延読み込み(Lazy Loading)を実装することで、表示領域に入ったコンテンツから順に読み込む方法も効果的です。
GoogleのPageSpeed Insightsなどのツールを使って、定期的に表示速度をチェックし、改善点を見つけることも重要です。これらのツールでは、具体的な改善提案も表示されるため、技術的な知識が少なくても対応しやすくなっています。

デザインでやってはいけないこと
ユーザーの第一印象を決めるデザインは、ホームページの重要な要素です。魅力的で使いやすいデザインを実現するため、以下のような失敗を避けましょう。
14. トンマナ(トーン&マナー)を統一しない
サイト内でフォント、色使い、デザインのテイストがバラバラだと、統一感がなく、プロフェッショナルさに欠ける印象を与えます。一貫性のないデザインは、ブランドイメージを弱め、ユーザー体験を損なう原因となります。
【解決策】 サイト全体のデザインガイドラインを作成し、統一性を確保しましょう。カラーパレット(メインカラー、アクセントカラーなど)、フォントの種類とサイズ、見出しのデザイン、ボタンやリンクのスタイル、画像の処理方法(枠線、角丸など)といった要素を一貫させることが重要です。
デザインの一貫性は、ブランドイメージの構築にも重要です。サイト全体で統一されたビジュアルイメージを維持することで、プロフェッショナルな印象を与え、ブランド認知度も高まります。
15. 過剰なアニメーションやエフェクトを使用する
派手なアニメーションや過剰なエフェクトは、ユーザーの注意を散漫にさせ、重要な情報に集中できなくなる原因となります。また、ページの読み込み速度も低下させます。
【解決策】 アニメーションやエフェクトは必要な場合にのみ限定して使用しましょう。効果的な使用例としては、ユーザーの注目を集めたい重要な要素、ユーザーアクションのフィードバック(ボタンホバー時など)、ページ内のナビゲーションをサポートする場合などが挙げられます。
アニメーションを使う場合も、シンプルで控えめなものにし、コンテンツの邪魔をしないよう注意しましょう。過剰な動きや点滅は、ユーザビリティを損ない、訪問者に不快感を与える可能性があります。
16. 視認性の低いデザインを採用する
背景色と文字色のコントラストが低い、文字サイズが小さすぎる、行間が詰まりすぎているなど、視認性の低いデザインはユーザー体験を著しく低下させます。
【解決策】 視認性の高いデザインを実現するためには、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。まず、文字色と背景色のコントラスト比を十分に確保しましょう。WebAIM: Contrast Checkerなどのツールを使用して確認することをおすすめします。
また、本文の文字サイズは最低でも14px以上(モバイルでは16px以上が理想)とし、読みやすさを確保します。適切な行間(line-height: 1.5〜1.8程度)を設定することで読みやすさが向上します。
段落間には適切な余白を設け、長文は適度に段落分けすることで読みやすくなります。高齢者や視覚障害のあるユーザーでも読みやすいデザインを意識することで、より多くの人にアクセスしやすいサイトになります。
17. ファーストビューを軽視する
ページを開いた瞬間に表示される領域(ファーストビュー)は、ユーザーの第一印象を決める重要な部分です。この部分が魅力的でないと、ユーザーはすぐに離脱してしまう可能性があります。
【解決策】 効果的なファーストビューを実現するためには、いくつかの重要な要素を含めることが大切です。サイトの主要メッセージやキャッチコピーを明確に伝え、ユーザーにとっての主要なベネフィットを簡潔に示しましょう。
魅力的なビジュアルを配置し、ユーザーの興味を引き付けることも重要です。また、明確なCTAボタンを設置して次のアクションを促し、ナビゲーションメニューを分かりやすく配置することで、ユーザーが求める情報に素早くアクセスできるようにします。
特に、「このサイトで何ができるのか」「どんな価値が得られるのか」をユーザーに明確に伝えることが重要です。最初の数秒でユーザーの興味を引くことができなければ、他のコンテンツがどれだけ優れていても見てもらえない可能性が高いことを忘れないようにしましょう。
コンテンツ作成でやってはいけないこと
サイトの核となるコンテンツ。ユーザーに価値ある情報を提供するため、以下のような失敗を避けましょう。
18. 他サイトの文章をコピペする
他サイトの文章を無断でコピーすることは、著作権侵害になるだけでなく、SEO的にも悪影響です。Googleは「複製コンテンツ」を検出すると、検索順位を下げる傾向があります。また、コピーコンテンツはオリジナリティがないため、ユーザーに価値を提供できず、専門性や信頼性にも欠けると評価されがちです。
【解決策】 必ずオリジナルのコンテンツを作成することが重要です。参考にする場合も、情報の引用にとどめ、文章はオリジナルで書くようにしましょう。引用する場合は必ず出典を明記し、自社ならではの視点や経験を加えることで、独自の価値を提供できます。
オリジナルコンテンツの作成が難しい場合は、プロのライターやコンテンツ制作会社に依頼することも検討しましょう。専門知識を持ったライターに依頼することで、正確で読みやすい文章を得ることができます。また、業界の動向や競合サイトの分析を行い、独自の切り口でコンテンツを作成することも効果的です。ユーザーが本当に知りたい情報を提供することで、コンテンツの価値を高め、結果としてSEOにも好影響を与えることができます。
19. 著作権フリーでない画像を使用する
インターネット上の画像を無断使用することは、著作権侵害となり、法的トラブルの原因になります。インターネット検索で見つけた画像や、他社サイトの画像を「引用」と称して使用しても、著作権法違反となる可能性が高いです。発覚した場合、高額な損害賠償請求を受けるケースもあります。
【解決策】 適切な画像を調達するためには、有料・無料の著作権フリー素材サイトを利用するのが一般的です。Shutterstock、Adobe Stock、iStockなどの有料サイトのほか、Unsplash、Pixabay、Pexelsなどの無料サイトも充実しています。また、自社で撮影した写真や作成したイラストを使用することで、オリジナリティの高いビジュアルを提供できます。予算に余裕がある場合は、プロのカメラマンやデザイナーに依頼することも検討しましょう。
特に注意が必要なのは、有名人の写真や他社の商品写真です。これらは無断使用しないよう徹底してください。また、著作権フリーの素材を使用する場合でも、利用規約をよく確認し、クレジット表記が必要な場合は適切に対応することが重要です。適切な画像使用は、サイトの信頼性向上にもつながります。
20. 大きすぎる画像を使用する
高解像度の大きな画像をそのまま使用すると、ページの読み込み速度が著しく低下します。特にモバイル環境では、大きな問題となります。一枚の画像サイズが数MBもあると、低速な通信環境ではページの表示に数十秒かかることもあり、ユーザーのストレスとなります。
【解決策】 画像は適切なサイズに最適化することが重要です。まず、表示サイズに合わせた画像サイズにリサイズしましょう。例えば、表示サイズが300×200ピクセルの場合に、元画像が3000×2000ピクセルでは大きすぎます。次に、適切な圧縮処理を行います。画質を大きく落とさない程度の圧縮であれば、ファイルサイズを50〜80%削減できる場合もあります。
最近のウェブ技術では、WebP形式など最新の圧縮フォーマットの活用も効果的です。これらの形式は従来のJPEGやPNGと比較して、同等の画質でもファイルサイズが小さくなります。また、必要に応じて遅延読み込み(Lazy Loading)を実装することで、画面に表示される部分から順に読み込むことができ、初期表示の速度向上に役立ちます。
画像の最適化には、Photoshopなどの画像編集ソフトの他、TinyPNG、Compressorなどのオンライン画像最適化ツールを活用すると簡単に行えます。こうした最適化は、ページ速度の向上だけでなく、サーバー負荷の軽減やモバイルユーザーのデータ通信量削減にも貢献します。
21. 専門用語や業界用語を多用する
業界の専門家にとっては当たり前の用語でも、一般ユーザーには理解しづらい場合があります。専門用語や業界用語を多用すると、情報が正確に伝わらない可能性があります。例えば、IT業界での「SaaS」「API連携」、建設業界での「躯体」「二次下地」など、専門家には当然の用語も、業界外の人には難解です。
【解決策】 分かりやすい文章を心がけるには、まずターゲットの知識レベルに合わせた言葉遣いを意識することが重要です。初心者向けのページでは基本的な用語から丁寧に説明し、専門家向けのページではある程度の前提知識を想定した表現を使い分けるとよいでしょう。
専門用語を使う場合は、初出時に簡単な説明を加えることで理解を助けることができます。例えば「API(他のソフトウェアと連携するための仕組み)を活用することで…」のように括弧内で簡潔に説明します。複雑な概念は、図や表を使って視覚的に説明することも効果的です。
長い文章は、適切な小見出しで区切ったり、重要なポイントを強調したりすることで読みやすくなります。ただし、あまりに簡略化しすぎると専門性が損なわれる場合もあるため、ターゲット層に合わせたバランスが重要です。専門性と分かりやすさの両立が、質の高いコンテンツの鍵となります。
22. ユーザーニーズを無視したコンテンツを作る
企業が伝えたいことだけを一方的に発信し、ユーザーが知りたい情報を提供していないと、ユーザーの関心を引くことができません。例えば、製品の機能や仕様を詳細に説明していても、ユーザーが知りたいのは「この製品で自分の問題が解決できるのか」という点かもしれません。ユーザーのニーズを理解せずにコンテンツを作ると、せっかくのホームページも効果を発揮できません。
【解決策】 ユーザーニーズに応えるコンテンツを作成するためには、まずターゲットユーザーの課題や悩みを深く調査することが重要です。アンケートやインタビュー、問い合わせ内容の分析などを通じて、実際のユーザーが抱える問題点を把握しましょう。
よくある質問(FAQ)を整理して回答することも効果的です。ユーザーからの質問は、彼らが本当に知りたい情報の宝庫です。これらの質問に丁寧に答えることで、ユーザーの疑問を解消できます。
競合サイトの内容を分析し、不足している情報を補完することも重要です。競合が触れていない点や、あまり詳しく説明していない部分を充実させることで、独自の価値を提供できます。
アクセス解析から人気コンテンツを把握し、関連情報を充実させることもおすすめです。アクセス数の多いページは、ユーザーの関心が高いテーマであることを示しています。そうしたテーマについて、さらに深い情報を提供することで、ユーザー満足度を高めることができます。ユーザーのニーズに応えるコンテンツは、結果的にSEOにも好影響を与えます。
SEO対策でやってはいけないこと
検索エンジンからの流入を増やすSEO対策は重要ですが、誤った方法は逆効果になります。適切なSEO対策を行い、持続的な集客を実現しましょう。
23. キーワードを詰め込みすぎる
「キーワードを多く入れれば上位表示される」と考え、タイトルやページ内に不自然なほどキーワードを詰め込むと、ユーザビリティが低下するだけでなく、Googleからスパム行為と見なされる可能性があります。キーワードの過剰な詰め込みは、「キーワードスタッフィング」と呼ばれ、Googleのガイドライン違反となります。

【解決策】 キーワードは自然な形で適切に配置することが重要です。タイトルタグにはメインキーワードを含め、見出し(h1, h2, h3など)に関連キーワードを自然な形で組み込みましょう。本文中では文脈に沿って自然にキーワードを使用し、違和感のない文章を心がけてください。また、メタディスクリプションには魅力的な形でキーワードを含め、ユーザーのクリックを促す内容にすることが効果的です。
現代のSEOでは、キーワード密度よりも、コンテンツの質と関連性を重視することが重要です。ユーザーにとって価値ある情報を提供し、検索意図に応えるコンテンツを作成することが、長期的な SEO 成功の鍵となります。
また、自然言語処理の発達により、Googleは単純なキーワードマッチングではなく、コンテンツの文脈や意味を理解する能力が向上しています。そのため、無理にキーワードを詰め込むよりも、トピックを深く掘り下げ、関連する用語を自然に取り入れた質の高いコンテンツを作成することが効果的です。

24. 被リンクを購入する
検索順位を上げるために被リンク(他サイトからの被リンク)を購入することは、Googleのガイドライン違反です。発覚した場合、検索順位の大幅な低下や最悪の場合はインデックス削除のペナルティを受ける可能性があります。Googleのアルゴリズムは年々高度化し、不自然なリンクパターンを検出する精度が向上しています。
【解決策】 正当な方法で自然な被リンクを獲得することが重要です。まず、質の高い、共有したくなるようなコンテンツを作成しましょう。専門性の高い情報、独自の調査結果、役立つガイドなど、価値のあるコンテンツは自然と他サイトから参照されやすくなります。
業界の専門家やインフルエンサーとの関係構築も効果的です。彼らにコンテンツを知ってもらい、評価されれば、自然なリンクにつながる可能性があります。また、他サイトでのゲスト投稿や業界メディアとの協力により、質の高い被リンクを獲得することもできます。
プレスリリースや業界ニュースの配信も、自然な被リンク獲得に役立ちます。ニュース性のある情報を発信すれば、メディアに取り上げられる可能性が高まります。信頼性の高いサイトからの自然な被リンクは、SEOに良い影響を与えるだけでなく、実際の訪問者の増加にもつながります。被リンク獲得は短期的な成果を求めるのではなく、長期的な視点で取り組むことが重要です。
25. 隠しテキストや隠しリンクを使用する
ユーザーには見えない形でキーワードやリンクを埋め込む「隠しテキスト」「隠しリンク」は、Googleのガイドライン違反です。
例えば、背景色と同じ色のテキストや、極端に小さなフォントサイズでのキーワード挿入などが該当します。これらの手法は「ブラックハットSEO」と呼ばれ、発覚した場合はペナルティの対象となります。
【解決策】 すべてのコンテンツは、ユーザーにも検索エンジンにも同じように表示されるようにすることが基本です。適切なSEO対策としては、自然な文脈でキーワードを使用することや、構造化データ(Schema.org)の実装が効果的です。構造化データを使えば、コンテンツの種類や属性を検索エンジンに明示的に伝えることができます。

26. メタディスクリプションを軽視する
メタディスクリプションは検索結果のページタイトルの下に表示される短い説明文で、クリック率に大きな影響を与えます。メタディスクリプションを設定しなかったり、適当に設定したりすると、ユーザーがサイトをクリックする可能性が低下します。Googleの検索結果でユーザーが最初に目にするのは、タイトルとメタディスクリプションであるため、この部分の最適化は非常に重要です。
【解決策】 魅力的なメタディスクリプションを設定するためには、まず適切な長さを意識しましょう。80〜120文字程度の簡潔な文章が理想的です。これは、検索結果で切れてしまわない長さでもあります。
メタディスクリプションにはページの内容を正確に要約し、ユーザーが期待する情報を明確に伝えることが重要です。主要キーワードを自然に含めることで、検索語との関連性も示せます。また、「今すぐ確認」「詳細はこちら」などの行動を促す言葉を含めることで、クリック率を高めることができます。
独自の特徴や価値提案を強調することも効果的です。例えば「業界最大級の品揃え」「24時間対応のサポート」など、競合との差別化ポイントを盛り込むことで、検索ユーザーの関心を引くことができます。
各ページに固有のメタディスクリプションを設定することも忘れないようにしましょう。同じメタディスクリプションを複数のページで使い回すと、検索結果での識別性が低下し、クリック率に悪影響を与える可能性があります。各ページに適切なメタディスクリプションを設定することで、検索結果でのクリック率を高めることができます。
27. モバイルSEOを無視する
現在、Googleは「モバイルファーストインデックス」を採用しており、モバイル版のサイトを優先して評価します。モバイルSEOが不十分だと、検索順位に悪影響を与える可能性があります。スマートフォンからのインターネット利用が主流となった現在、モバイルSEOの重要性はますます高まっています。
【解決策】 効果的なモバイルSEOのためには、以下の対策が重要です:
- レスポンシブデザインの採用: すべてのデバイスで適切な表示を確保
- ページ速度の最適化: 特にモバイルネットワークでの読み込みを高速化
- 使いやすいUI: 十分なサイズのボタン(最低44×44ピクセル)と適切なフォントサイズ(16px以上)
- シンプルなナビゲーション: モバイルでの操作を考慮した直感的な設計
Googleの「PageSpeed Insights」を定期的に活用して、モバイル対応状況を確認しましょう。モバイルユーザーの良好な体験は、SEOだけでなくコンバージョン率向上にも直結します。
運用・保守でやってはいけないこと
公開後の運用・保守も、ホームページの成功には欠かせません。継続的に価値を提供し続けるサイトを目指すため、以下のような失敗を避けましょう。
28. コンテンツを更新しない
公開後、長期間にわたってコンテンツを更新しないと、情報が古くなり、ユーザーの信頼を失います。また、Googleも「鮮度」を評価要素の一つとしているため、SEO的にも不利になります。更新されていないサイトは「放置されている」という印象を与え、企業の活動状況や信頼性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
【解決策】 定期的なコンテンツ更新を計画的に行うことが重要です。新商品・新サービスの情報を追加することはもちろん、ブログやお知らせを定期的に更新することで、サイト全体の鮮度を保つことができます。
古くなった情報は速やかに修正・更新し、最新の状態を維持しましょう。特に、価格、仕様、連絡先、営業時間などの重要情報は、変更があれば即座に更新することが大切です。
お客様の声や事例を追加することも効果的な更新方法です。実際のユーザーの体験談は、新規顧客の信頼獲得につながります。また、定期的に新しいページを追加することで、サイト全体のボリュームと網羅性を高めることができます。
更新頻度はリソースに応じて設定しますが、最低でも月1~4回程度の更新が理想的です。更新が困難な場合は、コンテンツ制作を外部に委託するか、社内での役割分担を明確にしてチームで運用することも検討しましょう。
また、更新計画を事前に立て、カレンダーなどで管理することで、計画的な運用が可能になります。定期的な更新は、検索エンジンへの良好なシグナルとなるだけでなく、リピーターの獲得にも貢献します。
29. アクセス解析を行わない
アクセス解析を行わないと、サイトのパフォーマンスや改善点を把握できず、効果的な改善が難しくなります。「どのページが人気か」「ユーザーがどこで離脱しているか」「どの流入経路が効果的か」といった重要な情報を得られないため、改善の方向性が定まりません。
【解決策】 効果的なアクセス解析を行うためには、適切なツールの活用が重要です。Googleアナリティクス4(GA4)やGoogleサーチコンソールは無料で使える基本的なツールとして広く利用されています。また、ヒートマップツール(Microsoft Clarity、Sitestなど)を併用することで、ユーザーの行動パターンをより詳細に把握することができます。
定期的にチェックすべき主な指標としては、アクセス数(PV、UU)、直帰率・滞在時間、流入経路、人気ページ、コンバージョン率などがあります。これらの指標を定期的に分析し、トレンドや異常値を把握することが重要です。
| 指標 | 内容 | 活用方法 |
|---|---|---|
| アクセス数 | ページビュー(PV)、ユニークユーザー(UU) | 全体的な人気度や成長の把握 |
| 直帰率・滞在時間 | ページを見てすぐ離脱する割合、サイト内での滞在時間 | ユーザー満足度やコンテンツの質の評価 |
| 流入経路 | 検索エンジン、SNS、直接アクセスなどの割合 | 効果的なマーケティング施策の判断 |
| 人気ページ | 最もアクセスの多いページ | 人気コンテンツの特定と類似コンテンツの強化 |
| コンバージョン率 | 目標(購入、問い合わせなど)の達成率 | サイトの最終的な成果指標 |
データに基づいて改善点を見つけ、継続的に改善することが重要です。例えば、直帰率の高いページは内容やデザインの見直しを行い、コンバージョン率の低いページはCTAの改善や価値提案の強化を検討するなど、具体的なアクションにつなげることができます。定期的なレポート作成と関係者での共有も、継続的な改善のためには欠かせません。
30. セキュリティ対策を怠る
ホームページのセキュリティ対策を怠ると、ハッキングやマルウェア感染のリスクが高まります。被害を受けると、ユーザーの個人情報漏洩、サイトの改ざん、Googleからの警告表示など、深刻な問題が発生する可能性があります。セキュリティ上の脅威となるセキュリティインシデントは、企業の信頼性に大きなダメージを与え、回復には長い時間とコストがかかることもあります。
【解決策】 ホームページのセキュリティを強化するためには、複数の対策を組み合わせることが重要です。まず、CMSやプラグインの定期的なアップデートを欠かさないようにしましょう。プラグインの脆弱性は日々発見されており、それに対応するアップデートが提供されています。特にWordPressなどの人気CMSは攻撃のターゲットになりやすいため、常に最新版を維持することが重要です。
また、ホームページ管理画面へのアクセスには、強固なパスワードを設定し、定期的に変更することも大切です。パスワードは12文字以上で、大文字・小文字・数字・記号を組み合わせたものが理想的です。二要素認証を導入することで、さらにセキュリティを強化できます。
バックアップの定期的な取得も重要なセキュリティ対策です。万が一ハッキングを受けてサイトが改ざんされた場合でも、バックアップがあれば迅速に復旧できます。サーバー上のバックアップだけでなく、外部のストレージにも保存しておくと安心です。
セキュリティプラグインの導入も効果的です。WordPressであれば、Wordfence、Sucuri、iThemes Securityなどの専用プラグインが利用できます。これらのプラグインは、不正アクセスの検知、マルウェアスキャン、ファイアウォール機能などを提供します。
より高度なセキュリティ対策として、WAF(Web Application Firewall)の導入も検討しましょう。WAFは、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングなどの一般的な攻撃パターンを検知し、ブロックすることができます。セキュリティ対策は一度行えば終わりではなく、継続的な取り組みが必要です。
31. 契約更新を忘れる
ドメインやサーバーの契約更新を忘れると、サイトが突然表示されなくなり、ビジネスに大きな影響を与える可能性があります。特にドメインの失効は深刻で、他者に取得されてしまうと、同じドメイン名を取り戻すのが非常に困難になることもあります。また、長年使用してきたドメインには検索エンジンでの評価も蓄積されているため、失うと SEO 面でも大きな損失となります。
【解決策】 契約更新を確実に行うためには、複数の対策を組み合わせることが効果的です。まず、契約更新日をスマホのカレンダーなどに登録し、十分な余裕をもって更新時期をアラートで知らせるように設定しましょう。例えば、期限の1ヶ月前、2週間前、1週間前にリマインダーを設定するといった工夫が有効です。
また、更新管理を複数の担当者で行うことで、担当者の不在や異動による更新忘れを防ぐことができます。主担当と副担当を設け、互いにチェックし合う体制を整えるとよいでしょう。
可能であれば自動更新設定を活用することも検討してください。多くのドメインレジストラやホスティングサービスでは、クレジットカードによる自動更新オプションを提供しています。ただし、クレジットカードの有効期限切れにも注意が必要です。
契約更新メールを確実に受け取れるよう設定することも重要です。更新通知メールが迷惑メールフォルダに振り分けられないよう、送信元アドレスをホワイトリストに登録しておきましょう。また、個人のメールアドレスだけでなく、部署のメールアドレスや複数の担当者のアドレスを登録しておくことで、通知の見落としを防げます。
ドメインやサーバーの更新管理は、ビジネスの継続性に直結する重要な業務です。適切な管理体制を整えることで、更新忘れによるトラブルを未然に防ぎましょう。
32. ユーザーからのフィードバックを無視する
問い合わせやSNSでのコメント、レビューなど、ユーザーからのフィードバックを無視すると、改善の機会を逃すだけでなく、ユーザーの不満が拡大する可能性があります。ユーザーフィードバックは、自社では気づかなかった問題点や改善点を発見する貴重な情報源です。また、フィードバックへの対応は、ユーザーとの信頼関係構築にも大きく影響します。
【解決策】 ユーザーフィードバックを積極的に収集し活用するためには、まず適切な収集チャネルを整備することが重要です。ホームページにお問い合わせフォームを設置し、アクセスしやすい場所に配置しましょう。フォームは簡潔で記入しやすいものにし、必須項目は最小限にすることがポイントです。
アンケート機能の実装も効果的です。サービス利用後や購入後に簡単なアンケートを実施することで、ユーザー体験に関する貴重な情報を得ることができます。SNSでのコメントモニタリングも忘れずに行いましょう。X(旧Twitter)やFacebookなどのSNS上での言及は、リアルタイムなフィードバックとして非常に価値があります。
定期的なユーザーテスト実施も検討してください。実際のユーザーにサイトを使ってもらい、使いやすさや問題点を直接確認することで、具体的な改善ポイントが見えてきます。
寄せられたフィードバックは、可能な限り迅速に対応し、サイト改善に役立てることが重要です。フィードバックに基づく改善を実施した場合は、その内容をユーザーに伝えることで、「声が届いている」という実感を持ってもらえます。また、頻繁に寄せられる質問や要望は、FAQページとしてまとめることも有効です。ユーザーフィードバックを尊重し、継続的に改善を行うことで、ユーザー満足度とロイヤリティの向上につながります。
ホームページ制作・運用で成功するためのポイント
ここまで「やってはいけないこと」を見てきましたが、最後にホームページ制作・運用で成功するための重要なポイントをまとめます。
ユーザーファーストの視点を持つ
すべての決定において、「ユーザーにとって何が最適か」を第一に考えることが重要です。美しいデザインや最新技術も、ユーザビリティを損なうようであれば価値がありません。ユーザーファーストの考え方は、ホームページの成功に直結する重要な要素です。
ユーザーの課題や悩みを深く理解し、それに応える情報を提供することから始めましょう。直感的なナビゲーション設計により、ユーザーが求める情報に素早くアクセスできるようにすることも大切です。また、重要な情報は分かりやすく目立つように配置し、ページ読み込み速度の最適化にも注力しましょう。スマートフォンやタブレット、PCなど、すべてのデバイスで使いやすさを確保することも忘れてはなりません。
ユーザーファーストのアプローチは、単なるデザインやコンテンツの問題ではなく、サイト全体の戦略に関わる考え方です。ユーザーの声に耳を傾け、継続的に改善を行うことで、長期的に支持されるホームページを構築できます。
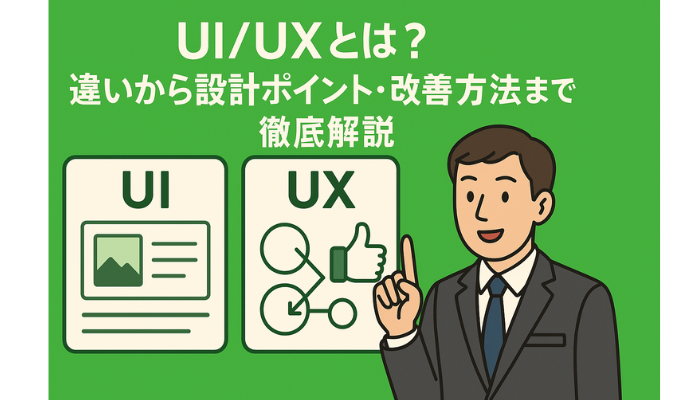
明確な差別化ポイントを示す
競合が多い現代では、「なぜ自社を選ぶべきか」を明確に示すことが重要です。自社の強みや独自性を効果的に伝えることで、競合との差別化を図り、ユーザーの選択を促すことができます。
差別化ポイントを示す際には、競合との違いを具体的に説明することが効果的です。例えば「業界最速の納期」「特許取得技術の活用」「24時間365日のサポート体制」など、明確な強みを前面に出しましょう。また、独自のサービスや特徴を強調し、お客様の声や実績を活用することで信頼性を高めることができます。
さらに、認定資格や受賞歴などの第三者評価を表示することも有効です。具体的な数字やデータで裏付けられた主張は説得力が増します。例えば「顧客満足度98%」「10年連続シェアNo.1」といった実績は、ユーザーの信頼獲得に役立ちます。差別化ポイントは、ホームページのトップページや「選ばれる理由」といったセクションで明確に伝えることが重要です。
専門家の知見を活用する
すべてを自社だけで対応するのは難しい場合もあります。必要に応じて、各分野の専門家の知見を活用することも検討しましょう。専門家との協働は、ホームページの質を高め、成果を最大化するための有効な手段です。
Webデザイナーや開発者は、見た目の美しさと機能性を両立したサイト構築に欠かせません。SEOコンサルタントは、検索エンジンからの流入を増やすための戦略を提供し、コピーライターやコンテンツマーケターは、ユーザーの心に響くメッセージの作成を支援します。また、UXデザイナーはユーザー体験の向上に専門的な視点を提供し、Webマーケティングコンサルタントは全体的な戦略立案をサポートします。
専門家に依頼する際は、自社の目標や課題を明確に伝え、緊密なコミュニケーションを取ることが重要です。また、すべてを外部に任せるのではなく、社内でも基本的な知識を身につけ、専門家と協働できる体制を整えることが望ましいでしょう。自社のリソースと専門家のサポートを効果的に組み合わせることで、限られた予算でも質の高いホームページ運用が可能になります。
まとめ
ホームページ制作・運用でやってはいけないことを、企画・設計、制作会社選び、サイト構築、デザイン、コンテンツ作成、SEO対策、運用・保守の各段階に分けて解説しました。これらのポイントを押さえることで、効果的なホームページ制作・運用が可能になります。
特に重要なのは以下の点です:
- 目的とターゲットを明確にすること
- ユーザーファーストの視点を持つこと
- モバイル対応とページ速度の最適化
- オリジナルで価値あるコンテンツの提供
- 適切なSEO対策の実施
- 継続的な更新と改善
ホームページは、単なる情報発信の場ではなく、ビジネスの成長を支援する重要なツールです。「やってはいけないこと」を避け、効果的な戦略を実践することで、成果を上げるホームページを構築・運用していきましょう。
最後に、ホームページ制作・運用は一朝一夕で完成するものではありません。継続的な改善と学習を通じて、徐々に成果を高めていくことが重要です。この記事が、皆様のホームページ制作・運用の一助となれば幸いです。

記事執筆・株式会社アクセス・リンク 代表取締役
Webサイト制作歴10年以上の経験を元にSEOコンサルティングを行い、延べ1,000件以上のサポート実績を誇ります。個人事業主や中小企業向けのホームページ制作やSEOコンサルティングを得意としています。
(社)全日本SEO協会 認定SEOコンサルタント


コメント